5月定例会のご報告
皆さん、こんにちは!
川崎つながろ会の杉田どぇす。
梅雨でもないのにぐずついた天気が続きますが、こんな時は読書に限りますね。
そんなあなたのために今回のひとりごとは「読書スペシャル」どぇす。お楽しみに!
それはさておき、皆様にご報告です。
5月26日の日本ALS協会の理事会において、
当会の髙野会長が日本ALS協会の副会長に任ぜられました。
日本随一の最先端ALS療養者である髙野会長がこの要職につくのは必然で驚きは当然ありませんが、今以上に多忙になるのではと体調を心配しております。
くれぐれも健康に留意しつつ、大役を全うされることをお祈りしております。
ここでカッコよく「あとはお任せあれ!」と言えればいいのですが、出来ないことは言うべきでないので静かにしておきますね。
では今回の定例会、さっそくなのですが!
川崎市立看護大学のボランティアサークル「川崎リンクス」に参加した新入生の内、お二人がボランティアとして外出支援のお手伝いをしてくれました。
この夏には学生ヘルパーのためのイベントもあり、学生ヘルパーの活動が静かに盛り上がりつつあります。
今後の活動にさらに注目です。
それでは「川崎つながろ会」5月定例会のご報告どぇす。
1.参加者
当事者:5名、当事者家族:2名、医療職:2名、介護職:1名、看護学生(川崎リンクス):6名、支援者(事務局):2名
2.軽く自己紹介と近況
支援者Oさん:歯が痛い。車いすの人に声を掛けたら、「お母さん…」と言われた。その呼び方どうなの?
当事者Nさん:自転車事故でご心配をおかけしましたが、もう大丈夫。就労移行支援事業所通い始めた。
医療職Sさん:訪問リハをやっている。四月に転職した。メタボ対策でご主人とキャッチボールを始めた。
新しい職場の言語聴覚士のKさんが本日リモートで参加。
杉田どぇすの家族:山梨の石和温泉に行き、飲んで、飲んで、飲んできた。
看護学生Tさん(新):チョコプリンを作った。
介護職Tさん:アプリ開発をやってみたい。
看護学生Tさん:アフタヌーンティーに午前行った。
看護学生Eさん:髙野会長のヘルパーをやっている。やる事が沢山ある。
髙野会長:生成AI環境のファイルサーバーを作った(?) 不眠は改善した。
看護学生Wさん:推しアイドルのライブを武道館に観に行った。
看護学生Yさん:GWに初大阪旅行に行った。外国人が多く、生関西弁は聞けなかった。
当事者佐藤さん:「難病と在宅ケア」に寄稿した記事が掲載された5月号が出ました!看護学校での講演準備中。
佐藤さんのご家族:駐車の際手間取ったが、看護学生Yさんの笑顔により周りの人は皆優しくなり助かった。
小学校で日本来た外国人に教えている。日本語が喋れる様になってきた。「やすこ」という名前は古いと思っていたが小学生にウケた。
杉田どぇす:何もない平和な日々だった。ヘルパー達と新城のカフェに行った。
当事者Uさん:介護事業所ヘルパーの給料を払えた。
2.業務連絡
・海老原ひろみ基金
昨年度助成金をもらい学生ボランティアへの支払い等に活用。報告会が7/28にオンラインであり、5分間の動画を撮影しなければならない。
今年度も申請する。6/1が申込期限。
3.お悩み相談
Q.医療行為問題。家族が夜間不在でヘルパーにケアをお願いする際、NPPV(※)のスイッチを押す事が医療行為にあたるので、今後方法の検討が必要となった。(※)マスクを装着するタイプの夜間呼吸補助装置
A.
・スイッチを押してアラームが鳴ったり、何か起きた時の対応を決めておくなどのサポートが必要。
・事業所のヘルパーは呼吸器を触らない。水抜きのため換気を一時的に止める事も同様。
・グレーゾーン。自薦ヘルパーで本人合意の場合はできる。
・薬の注入、服薬も同様。家族に説明してくれる際「ヘルパーはダメ」と言われたがミスが起こらないよう指導してもらった上で理解してもらった。
・ヘルパーに許されている事もドクターの指示書が必要でそれは三か月毎更新。ヘルパーによる吸引も看護師会は反対した。
在宅生活をしたいのなら看護師を雇えと言う医師もいた。さよならした。
・基本説得はしない。撤退すると言われたら終わり。言いなりが平和。
・横浜に良い訪問看護ステーションがあった。
Q.使っているコミュニケーション機器と理由を教えて欲しい。
A.
・秋にコミュニケーションについて「難病と在宅ケア」に寄稿する。
・Hearty Ai。無料、自分のPCで使いたいから。
・横浜福祉機器支援センターに頼んで二つ試した。TCスキャンとOrihime。Orihimeは画面が動く所に向き不向きが出るようだ。
FBを見てライフハックの伊藤さんに来てもらった。補助金について地域情報に詳しい。補装用具と日常で給付は別。
注:リハビリや療養生活に関することは必ず医師や看護師などの医療者や、
作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などの専門職の方と相談しながら進めてください。
4.今後の予定
6月定例会は6月16日(日)・13時30分から16時、川崎の「福祉パルたかつ」にて開催いたします。
オンラインでも参加可能です。どなたでもお気軽にご参加ください。
今回のひとりごと、何と書籍を4冊もご紹介。
そもそも、なぜこんな病気や療養生活に関係ないひとりごとばかりしているのかというと、
こういうものたちが私をしなやかにしたんだと感じるからなんだよね。
山、音楽、写真、映画、漫画、イラストなどなど、これらは私にとって生きるために必須のもの。
病気になって振り返ってみた時、こういうものたちのおかげで割といい人生を送ってこれたなと思うところがあった。
だから病気で大して動じることもなかったし、次のステップにも行けたんだと思う。もちろん、だけじゃないけど。
今、目いっぱい楽しんでください、ってことです。そのためにちょっとした情報提供をしてる。そんな感じで書いてます。
さて。
講釈はこのくらいにして、まずは写真の本を二冊ご紹介。
最初にワタナベアニさんの
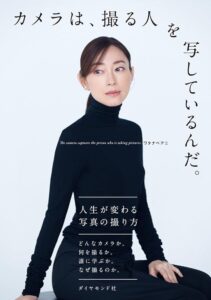
そして幡野広志さんの
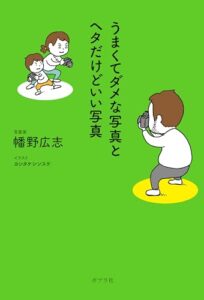
どぇす。
みんな、どんな時にシャッターを切るのかを考えたことがあるだろうか。
目の前にのある景色。
誰かがいたり風景だったり。
その目の前にある何かに心が反応したのは間違いない。
その目の前にある何かを切り取って残しておきたいと思ったわけだ。
その目の前にあるものが何であれ、それはその人にとってポジティブなものであるはずだ。
ということは、「写真を撮る」という行為は誰にとってもポジティブな行為のはずだ。
だから、みんなに写真を撮ってほしい。
人、物、風景。
「それを残そう」
そう思ったらシャッターを押そう。
そうしてさやかな喜びや楽しさを積み重ねて愉快に生きよう。
そんな気持ちでこの二冊を紹介します。
前者の本はSNSにアップした写真がたまたまバズった青年と謎の写真家とのやり取りを中心に進む。
印象深かったのは、「写真は文学だ」のくだり。何か小難しい話しか?と思いきや、読めば納得のお話。
むかし、自分が選んだりよく売れたりしたプロダクトについて「なぜそれが選ばれたのか」を言語化していたのを思い出した。
仕事のトレーニングのつもりだったけど、これが結構面白くて今でも「あれはなぜヒットしたんだろ」なんて考えたり。
このあたりから徐々に深くなっていくが、二人の軽妙なやり取りで楽しく読み進められる。
後者の本は「いい写真は感情が伝わる写真」と言っていた。
じゃあ伝わる写真ってどんなの?どうすれば撮れるの?また、「いい写真はうまい写真じゃない」とも。
写真には「うまくていい写真」「うまいけどダメな写真」「ヘタだけどいい写真」「ヘタでダメな写真」があるという。
じゃあ「うまい」って?「ヘタ」って?「ダメ」って?
そうしてお話が始まるのでした。
ゴリゴリの技術的なことはあまり書かれていないが、現像についてはボリューム多め。
確かにRAWで撮って現像すると写真って劇的に変わるもんなぁ。
jpgじゃなくRAWで撮って現像する。これだけで写真がより楽しくなると思う。
10年前のデータもRAWで撮っとけば現像ソフトが進化してるから昔現像したデータとは違った現像ができる。
そんな楽しみもあるんじゃないかな。私は現像、苦しいけど楽しいです。
続いて三冊目は岡田悠さんの

「旅」といえばどこか遠くの場所に移動することが前提とされているけど、本当にそうだろうか。
10年以上前、南アルプスの鳳凰三山を縦走した。夜明け前、テントを片付けザックを担いで出発し、しばらく歩いて稜線に出た。
突然視界が開けると、目の前に北岳、間ノ岳、農鳥岳の白峰(しらね)三山とそれらの巨大な尾根が悠然と並んでいた。標高3000mの縦走路だ。
この数カ月後、白峰三山を歩くわけだけど、この縦走は鳳凰三山の稜線で見たときから始まっていたんだと思う。
情報を集め、何度も何度も雑誌の写真を眺めては妄想にふける。もう旅は始まっていた。
ま、そんな妄想の旅本ではなく、実際に著者の岡田悠さんが旅をした記録なのだが、笑いあり、涙ありの体験記だ。
この本、最初のお話が南極で距離にして1635万メートルから始まり、徐々に0メートルに近づいて来るという構成になっている。
最後どんな旅で終わるのか。岡田さんらしい旅で締められてるなあと感じた。
岡田さんの旅の特徴は旅先の選び方だ。この人の旅は行き先が決まる前から始まっていると言っていいだろう。
もしかしたら「すべてをぶち壊したい」と心が叫んだとき、旅はすでに始まっているのかもしれない。
身体が自由に動かない私は毎日が「0メートルの旅」だ。でも、そこにも旅の本質があるんじゃないか。
そんなことを語りかけているように感じた。
ラスト四冊目は岩永直子さんの
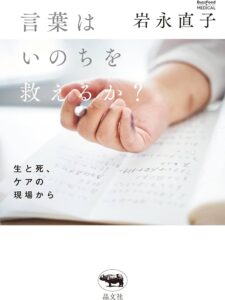
これは医療記者である岩永さんのノンフィクション。
難病患者生き様、人の価値と生産性、安楽死について、グリーフケアについて、終末期医療費の議論についてなど、
読む前から興味のあるお話だけでもこれだけある。じっくり読んだ。
いのちを救う。
これがどれほど困難なことかは、何人もの患者仲間が延命せず逝ってしまった事実からしても明らかだ。
言葉でいのちが救えたなら、この世の悲しみや辛さはもっともっと少ないはずだ。
そんなことを考えながら読み進めようとした。
まず本編の前の「はじめに」がちょっと衝撃というかかなりヘビーだった。
「はじめに」を読むと、岩永さんの「言葉」と「いのち」は一般的な人たちとは少し意味合いが違うのかもしれない。そう思えた。
一つ一つの記録はどれも問題の本質を探り明らかにしようとしているんだけど、
その姿勢は記者としてというよりも、岩永さんの宿命がそうさせているんじゃないかと思えてくる。
読み終えてみて最も考えさせられたのは、やはり最後の「家族性大腸ポリポーシス当事者」のお話。
この本のタイトルもこのお話がつけさせたんだろうな、と思う。
たった一人の家族である母が、最愛の息子のためにノートに綴った魂の言葉。
その言葉を息子はどのように受け止めたのか。
そして、その言葉はいのちを救ったのだろうか。
ぜひ読んで確かめていただきたい。
去年から「境を越えて」というNPO法人に協力する形で医大生を半日だけだが受け入れている。
今年もあると思うのだが、医療に携わる者は読むべきだと、この本を推薦するつもりだ。
以上、写真、旅、いのちの三つのカテゴリーの本をご紹介しました。
どれか一冊でも手に取っていただき、心に響くものがあったとすれば望外の喜びです。
それでは皆さん、毎日を楽しみましょう。




こんにちは。
以前からとても気になっていた「川崎つながろ会」。
読ませていただいて、機会を作ってぜひ参加したいなとワクワクしました。
高野会長、日本ALS協会副会長就任おめでとうございます!
いろいろご相談したいこともありますので、今度うかがわせてください。
川崎つながろ会様のこれからますますのご発展をお祈りしています。
ともみんさま
読んでいただき、またコメントまで頂きありがとうございます。
いつでもお気軽にご参加ください!みんなでお待ちしています。
こちらのメアドは当会のメーリングリストに登録しているでしょうか?
もしまだでしたら登録させていただき、オンライン参加のアドレスをお送りいたしますのでご検討ください。
それではお会いできる日を楽しみしております。